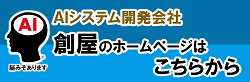子供といっても中学に入ったぐらいの話し.もう50年くらい前の話しになる.
小学校のときは,勉強が嫌いとか,なんでこれを勉強するのかとか,まったく感じたことが無かった.
それが中学になって,地理と英語の学習で,なんだこれは・・・と思うようになった.
なぜ,覚えないといけないのか? 記憶しないといけないってなんで? って.
地理で,日本全国の山脈を覚えろとか,工業地帯の名前を覚えろとか,意味わからん.それが,なんの役に立つのか.
地図を見れば,そこに書いてあることを暗記する意味が分からない.
英語も,同様だ.覚えることばっかり.
腑に落ちないと,頭に入らない子供だった.頭に入らないどころか嫌悪感すら持つような感じだった.
数学や理科は,すんなりでもないけど,大丈夫だった.
社会の中でも,なぜか歴史は好きだった.公民もまぁまぁ大丈夫だった.
いったい,なんだったのだろう.
地理は,あちこちに行くようになり,街や工業地帯や自然いっぱいの山の中を実際に見るようになって感覚は変わったけど.
なぜ,その地域に,それは存在するのか? ということを考えるようになってから,勝手に頭に入るようになった.
英語は,今でも嫌い.文法の話をされると,もう頭がフリーズする.
最近,会社では,抽象化の話しが出ている.
抽象の反対は具体となるわけだが,具体というのは,末端のそれぞれの事象やモノだったりする.場合によっては,時系列も伴う表現になる.
抽象化すると,それらはまとめられ,どんどん数が減っていく.
この抽象化こそが,僕にとっての腑に落ちるということだったのかもしれない.
中学以降の数学は,xにyといった記号が中心になる.いわば抽象化の塊だったわけだ.
概念を理解するということで,応用が出来るようになる.
具体的なものは忘れても,上位の抽象化されたものから,導き出すことが出来るようになる.
ここの能力が仕事のスピードを決める.
と同時に,表現力も問われるようになっている.
抽象化は一つではない.複数の段階が存在する.レベルを合わせて話をしないと,頭の中で描いているものが人によって異なることになる.
ここは,日本語能力やコミュニケーションの技術的なものが大事になってくる.
結局,別の集団の,多くの人たちと,どれだけ接してきたかが,肝なのかもしれない.
趣味の集団+趣味の話しであれば,あれこれ説明しなくても相手に伝わることが多いだろう.それに慣れてしまうと,コミュニケーション能力は落ちてしまう.
色んなバックボーン,色んな考え方を持った人たちと関わることが,コミュニケーションを鍛えるために必要なんだと思う.
学生時代,色んなアルバイトをしたけど,そういう経験が役に立っているのかなぁ,と想像している.
社会人になっても,結構,出張に行ったし.今も行ってるし.
あと,本は,山ほど読んだ.
小説も自己啓発本も.
ベストセラーと言われた本は,積極的に手に取るべきだと思う.
最近の若者の活字離れは嘆かわしい.
スマホ,SNSは,害悪だ.時間の使い方をもっと考えたほうがいいぞ,若者たち!