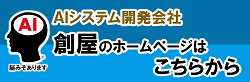東アジアにおける人口動態の課題
2023年、韓国の女性1人あたりの出生率はわずか0.72と、世界最低水準にあります。高騰する住宅費、教育費、雇用の不安定さが子育ての経済的負担を増大させ、多くの人が出産を先延ばしまたは断念する要因となっています。この現象は、伝統的な家族形態よりもキャリアや自己実現を重視する社会全体の変化を反映しています。
韓国の未来への影響
この傾向が続けば、2060年までに韓国の人口は30%減少し、国民の半数が65歳以上になると予測されています。急速な労働力人口の減少は、年金、医療制度、経済全体の持続可能性に深刻な打撃を与える恐れがあります。一部の予測では、軍の採用難が進み、女性の徴兵を検討せざるを得ない状況や、年金制度の崩壊が懸念されています。
日本と中国との比較
-
日本:
2022年の出生率は1.26で、韓国より高い状況にあります。特に東京以外の地域では住宅費が比較的手頃であり、エリート教育への過度な投資も求められにくい環境が背景にあります。伝統的な性役割(女性が家庭内責任の80%を担う)が根強いものの、トヨタの残業削減など企業の取り組みが徐々にワークライフバランスの改善に寄与しています。 -
中国:
中国の平均出生率は約1.7ですが、地域ごとの差が大きいのが現状です。都市部ではソウルに似た高い住宅費や育児費用の負担があり、一方、農村部では貧困やかつての一人っ子政策(1980~2016)の影響による男女比の偏りが問題となっています。政府は育児補助金などのインセンティブと中絶規制などの強制策を併用して、家族規模に影響を与えています。
政策対応と社会の変化
-
韓国:
補助付き住宅リースや無利子ローンといった積極的な少子化対策により、2024年には出生率が0.75まで僅かに上昇しました。しかし、職場の性差別や教育費の高騰といった根本問題が依然として解決されておらず、「4B運動」(恋愛、結婚、出産、異性愛関係の拒絶)が家父長制や不平等な家庭内負担への反発として広まっています。 -
日本:
日本の政策は、普遍的な保育、延長された父親の育児休暇、及び大幅な出産補助金によって親の負担を軽減することに重点を置いています。これに加え、控えめな移民改革や地方の活性化施策も、労働力不足の緩和に寄与しています。さらに、ロボットやAIの活用が、急速な高齢化社会への対策として進んでいます。 -
中国:
中国政府は、プロパガンダと具体的なインセンティブを通じて大家族を推進する一方、未婚者や子供のいないカップルにはさまざまな制限を課す二重戦略を取っています。しかし、2024年には若年層の失業率が21%に達するなど、経済的現実が政策の効果を大きく阻害しています。
韓国、日本、中国は、それぞれ独自の背景と課題を抱えながら、低出生率という共通の問題に直面しています。韓国では過度な競争と性別不平等が根深く、経済的インセンティブだけでは解決できない構造改革が求められています。一方、日本は伝統と近代化のバランスを取る慎重かつ実践的なアプローチを試みているものの、その効果に限界が見える状況です。中国は、インセンティブと強制策を組み合わせた政策で、上からの介入が社会経済的格差の解消には容易でないことを示しています。これらの国々が未曽有の人口動態の変化にどう対応していくかが、今後の国の未来だけでなく、後工業社会における世界全体の動向にも大きな影響を与えるでしょう。